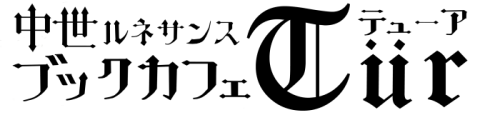店内看板の祭壇画を古典技法で。白亜地の地塗りを板パネルに行いました!
≪スポンサーリンク≫
看板は、お店の顔とも言えるとても大事な存在です。
とにかく目立たせい!と思って、私は前から「祭壇画」風の看板が作りたいと考えていました。
祭壇画とは絵やレリーフで飾ったパネルを2枚~多数つけた、教会の祭壇飾りのことを指します。と言っても教会内だけではなく、持ち運びのできるコンパクトサイズのものや、王宮や貴族屋敷に飾られたものも多くあります。中世以降になると中央と左右にパネルをつけた「三連祭壇画」がメジャーとなります。
私の師匠である北方ルネサンスの巨匠、ヒエロニムス・ボスの代表作「快楽の園」。こちらが三連祭壇画となります。


扉を閉じたところには天地創造の絵が、開いたところには神がアダムとイヴを創造した場面、地上の楽園、地獄が描かれています。幻想性や謎が溢れた、素晴らしい作品ですね…。
と、三連祭壇画の美しさを伝えましたが、私が作ろうとしている店舗看板は「なんちゃって三連っぽい祭壇画」です^^;
看板となる祭壇画の姿はこちら!


黒光りするボディ、斜めを描くシャープな上部、凹のある表面。荘厳さと慇懃さを称えた、上品な祭壇画!
でも、描くのは中央パネルオンリーです!w
時間的に考えて、流石に3枚パネルを描くのは難しい…。余裕があったら装飾くらいはやりたいなぁと思っています。
こちらの祭壇画は数年前にリサイクルショップにて購入しました。もともと中央にはダーツの的の機械が入っていまして、当てると光る仕様だったようですが、壊れてしまっていました。またダーツの付属品もなく、安く販売されていたものです。
まだブックカフェをオープンさせようとは決意していなかった頃でしたが、「これ…祭壇画になりそう。何かにつかえるかも!」と思って購入、的の機械の部分を取り外して、物置に長くしまったままになっていました。昔の私、ナイス判断です。
この元ダーツの的の祭壇画を、お店の看板として生まれ変わらせたいと思います。
今回は中央パネルの板づくりと白亜地の地塗りを行ったので、お伝えします!
中央の板づくり

中央パネルとなる板は、家に長く眠っていた板を使います。厚さは5mm程度のもの。おそらくシナベニヤです。写真は裏面部分で、縦に少しひびが入っています。
サイズを測って線を引き、線を目安に糸ノコギリで切っていきます。切ったあと、ちょうど中央にはまるように端をやすりがけをしました。
文章を書くと容易く感じますが、これらの作業が超大変でした^^;
家にある糸ノコギリの切れ味が悪くてひたすらぎこぎこと切り、手を変え品を変え色々と工夫しましたが、やっぱりうまく切れずに時間がかかってしまいました…。
やっと切れたやったー!思ったら、ピタッと中央にはまらない。一回では無理だろうなぁと予想はしていましたが、中央にきちんとはまるまで、ひたすら側面をやすりがけするのは非常に骨が折れました…。
いい道具と技術があれば早いのでしょうが、素人の木工ではしょうがないですね^^;
ノコギリとやすりがけで、結局半日かかってしまいました。

頑張った甲斐があり、中央パネルが完成!
表面は軽くやすりがけを行いました。次は、膠水を作って塗っていきます!
板パネルに膠水を塗る(前膠)
まずは、膠(にかわ)を水に溶かして板パネルに塗っていきたいと思います。
膠は動物の身体から抽出された、ゼラチンを主成分とする物質であり、古代より接着や絵画の下地剤などに用いられてきました。日本画でも使われていますね。

こちらの粒膠は大学時代に使っていたものです。眠っていたものを物置の奥から発掘。すっごく久しぶりに扱うので、ほぼ覚えていない…。昔の資料を引っ張り出して確認します。
膠水のつくり方&塗り方
- 水に対し、10%の膠を用意。(私は水40mlに対し、4gくらいの膠を用意)
- 膠を水へ投入。ラップをして、そのまま5~6時間くらい芯がなくなるまで待つ。(粒膠だとこれくらい。粉だともっと早いし、棒だと遅いと思います)
- 膠がぷるぷるになったら、お鍋に80℃くらいの湯を用意。ボールに入れた膠水を、湯煎にかけて溶かします。温まって完全に溶けたら完了です!
- 刷毛を使って、まだ温かい膠水を薄くまんべんなく塗っていきます。塗れたら乾かします。
- 裏面や側面も同様に塗っていきます。膠水が冷めてはいけないので、冷えてきたら再湯煎をしてください。
- 乾いたら再度、表裏を塗ります。その後、必要に応じてやすりがけをします。



前膠はこれにて終了です!
色々と調べると、サイトによってやり方が分量がまちまちとなりますが、私が学んだ手法で行いました。次に、白亜を使って地塗りを行いたいと思います!
≪スポンサーリンク≫
白亜の地塗り
白亜の地塗りは、中世ルネサンスの画家がテンペラや混合技法(テンペラと油彩の両方)の板絵を描くために行っていた、古典的な技法です。主にフランドルやドイツ地方の画家が白亜を用いていました。イタリアでは石膏を使っていたようです。
白亜地や石膏地は絵具の油分や水分を吸収するために吸収性下地と言われ、絵具がよく乾き定着するとされています。
白亜は主にサンゴや貝などの死骸が化石となった「炭酸カルシウム」が原料。基本、白亜と膠水を混ぜて下地材を作ります。
私は重質炭酸カルシウムと膠水、下地を白くするためにチタニウムホワイトを用いました。こちらも大学時代の資料を引っ張り出し、最近の情報と照らし合わせながら行いました。
なお、これらの材料は皮膚や目に入ると有害です。手袋やマスクなどを着用して、直接触れないようにしましょう!もし触れた場合はすぐに洗い流してくださいね。
では、早速やっていきましょう!
下地材のつくり方&塗り方
- 白亜(1.5)+チタニウムホワイト(0.5)=10%濃度の膠水(1)+水(1)の分量を用意。200gの白亜地を作るなら、白亜75g+チタニウムホワイト25g=膠水50g+水50gという感じです。粉類と水分が同じ比率となるようにします。
- 80℃の湯煎用のお湯を用意します。粉類はダマにならないよう、ふるいにかけましょう。
- ボール(小鍋)に膠水と水を入れ、その中に粉類をゆっくりと入れます。【注意】粉は有害なので、これらの作業は外でやった方が無難です。私も外で行った後、キッチンへと運びました。
- 湯煎を行いながら、しばらく水と粉を馴染ませ、ダマと空気が残らないよう混ぜていきます。
- しっかりと混ざっていることを確認したら、刷毛を使って板パネルの表面を塗ります。一定方向で塗りましょう。15~25分ほど乾かします。
- 乾いたら裏面を塗っていきます。できたら再度乾くまで待ちます。
- 表面に戻し、2層目を塗っていきます。白亜の層を一定にする為、刷毛の塗る方向を変えてください。(1層目横方向なら、2層目縦方向へ)またもや乾かします。
- 2層目の裏面を塗り、乾かします。時間がかかりますが、辛抱辛抱…。
- 塗る方向を変えて、3層目の表面を塗ります。諸説ありますが、白亜地の塗る層はだいたい3層目くらいで大丈夫です。これが乾いたら白亜地の塗りの完成です!
- このままでは表面がぼこぼこですので、最終仕上げとしてやすりがけがあります。つるっつるになるまで磨き上げます。




根性のやすりがけ
表面がぼこぼこなままだと、混合技法で絵画を仕上げた際に光沢感のある滑らかな輝く画面が生まれません。
一晩~数日置いて完全に乾かした後、つるつるの表面になるまで、ひたすら表面を紙やすりで磨いていきます!
こちらも削り粉がかなり飛ぶので、行う際はマスクや手袋の着用をしましょう。また、地面に粉が付くと落ちなくなります。ご注意くださいね。(我が家の玄関が白くなりました…汗)
最初は180の粗い紙やすりを使用、段々と300~600と細かいものを使って表面を綺麗にしていきました。
なかなか滑らかにならない。磨いても磨いても凹みが気になる…。一人、無言でひたすら白いパネルとやすりと向き合い、段々と無我の境地に陥ってきました^^;
段々とキリがなくなり、程ほどのところで終わらせました…。

完璧とはいかないものの、滑らかな表面になりました。これで白亜地は完成となります!
これらの作業をやっていると、中世ルネサンスの画家ギルドの皆様の大変さがよく身に沁みます…。地塗りを行うだけで、体力を使うし工程が多い。この先、色彩豊かな色を乗せるのに、まだまだ多くの工程が必要になります。
次回は下絵が完成でき次第、白亜地に転写を施していきたいと思います!
次回へ続く!